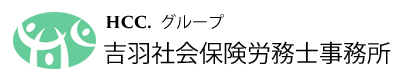カテゴリー:最新情報の一覧ページです。
先週、3年ぶりの沼津夏祭りが開催されました。
弊所の近くの狩野川近辺では、大きな花火を楽しむことが出来ました。
数年ぶりのお祭りに、久しぶりの「夏」を感じた方も多かったかもしれませんね。
感染症の急拡大と併せて、熱中症にも十分気を付けなければならない季節です。
一旦落ち着いた暑さですが、来週以降はまた気温が上がり「熱中症アラート」が発令しそうです。
勤務中の熱中症対策もしっかりとしていくことで、健康被害を防ぐことができます。
近年の猛暑では、社内・社外に関わらず熱中症にかかることがあります。
水分・塩分の補給、クーラーの適切な使用、併せて換気をしながらの
感染対策と、会社全体として・1人1人の従業員の健康を守るために
今一度熱中症について正しい知識を確認しておきましょう。
厚生労働省から、熱中症予防のための情報が発表されています。
ご一読ください!
※※熱中症予防のための情報※※
ここ数日は梅雨の戻りのように、すっきりしないお天気が続いています。
静岡県では、富士山の山開きが始まりました。
近いからこそなかなか登山をチャレンジする機会を持てないものですが、いつかは、、、
富士登山へ挑戦してみたいです。
さて、今年の4月1日から法改正となった「育児・介護休業法」は、3段階で施行されていきます。
次回は今年の10月の施行となり、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・育児休業の分割取得が
改正ポイントです。
男女問わず仕事と育児を両立でき、安心して取得できる社会への一歩になりそうです。
厚生労働省の資料です。ご一読ください!
令和4年4月法改正~育児・介護休業法
静岡県も10日程前に梅雨入りをして、ジメジメとした日が続いています。
まもなく7月を迎えますが、明日からは早速気温が上がり暑くなります。
今年は梅雨明けも例年より早くなりそうで、長くそして暑い夏がやってきそうですね。
厚生労働省からは、熱中症予防や対策のためのリーフレットがでています。
ぜひ、ご一読ください!
厚生労働省/熱中症対策
厚労省 熱中症予防&コロナ対策
マスクによる熱中症も心配されます。特に仕事中は集中をしているため、
体に必要なものが不足になりがちですので、屋内・屋外の業務に関わらず積極的に水分・塩分の
補給を心がけていきましょう!
新緑がキラキラと輝き、様々なものが伸び行く姿に出会える季節になりましたね。
若葉のようにフレッシュな皆さんに今年も出会い、恒例の新入社員研修(クローズタイプ)を
数社実施いたしました。
毎年、テーマやスタイルを変えてブラッシュアップしています。
今年は、通常の研修に加え「コンプライアンス」「接遇」「伝わる声とは」等
新たな視点で行いました。
弊社では、今関心度の高い「ハラスメントに関する研修」も行っております。
新入社員、管理職向け、一般社員向けとご要望にあった研修を整えておりますので
こんな研修をして欲しいというお声をぜひ聞かせてください。
皆様からのご相談をお待ちしております。

毎年のことですが、1月2月の過ぎるスピードは本当に早く、来週からはもう3月です。
そろそろ花粉症の方は辛い日々が始まるでしょうか。
先週までは北京オリンピックに背中を押され元気をもらいました!
来週からは北京パラリンピックも始まりますね。今年は、例年以上に色濃く変化の多い1年と言えるかもしれません。
雇用に関する法律でも変更点があり、年度の途中で雇用保険料率が変更されます。
2022年2月1日、政府は定例閣議において、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを閣議決定しました。
現在は労使合わせて賃金の計0.9%を負担する保険料率が、今年の4月から9月は0.95%へ。
具体的には、事業主のみが負担する雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険二事業)に係る料率が、
0.3%→0.35%に変更されます。
新型コロナの影響で雇用調整助成金の給付が膨大なものとなり、今回の保険料引き上げになったと考えられます。
さらに年度の途中、今年の10月から来年3月は1.35%に引き上げられる予定です。
現在は労働者負担0.3%、事業主負担0.6%
→労働者負担0.5%、事業主負担0.85%
4月から保険料率は変わりますが、被保険者の従業員さんが負担する分に限り10月からの変更となります。
給与計算に影響があるのは年度の途中からになります。
10月からは給与計算の際に、雇用保険料率を変更する必要がありますので十分ご注意ください。
何か不安な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

事務所の葉っぱも春めいてきました
北京オリンピックが始まりました。
静岡では雪に触れてスポーツをする機会はなかなかありませんが、選手たちの滑りやジャンプを見ていると、
ゲレンデに出かけてみたい気持ちになりますね。
スポーツというと、昔は「スポ根」アニメで厳しいコーチがつきもので、
今の時代では「NO!」なことも度々描かれていたのではないか、と思います。
時代は刻々と変化し、職場でのハラスメント対策は非常に重要になっています。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が改正されたことに伴い、今年の4月から中小企業にも
職場におけるパワハラ防止対策が義務化となります。どんなことが義務化されるのでしょうか?
「パワハラ防止」に取り組むべき4つの義務とは?
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発をする
2.相談(苦情含む)に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備をする
3.職場におけるパワーハラスメントにへの事後の迅速かつ適切な対応をとる
4.上記の措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護・不利益取り扱いの禁止等必要な措置をとる
厚生労働省リーフレット→パワハラ対策の義務化
ぜひご一読ください。
今後は、各企業において準備や対応が必須の課題となるでしょう。
当事務所では、パワーハラスメント発生後の対応に関する相談だけではなく、パワーハラスメント防止に関する社内研修などにも応じさせていただきます。
少しでも不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
もうすぐ立春ですが、厳しい寒さに加え新型コロナの第6波の影響が心配ですね。
外でお酒を飲む機会も以前よりは減っている昨今ですが、飲酒運転による悲惨な事故を防ぐために
この4月1日から改正道路交通法施行規則が順次改正されることになりました。
【改正のポイント】~安全運転管理者によるアルコールチェック~
「車5台以上使っている会社」または「乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する会社」では
安全運管理者の届け出が必要になります。
安全運転管理者に義務付けられること→
・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認。
・目視およびアルコール検知器による確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存。
・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。
さらに10月1日からは、
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行う。
・アルコール検知器を常時有効に保持。
安全運転管理者を選任する事業所では、運転前後における点呼等、
記録の明確化やアルコール検知器の導入に向けて早めの準備をしていきましょう。
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、今後この基準に基づいて、労災補償が行われていきます。
今回の改正は約20年ぶりで、注目すべきは労働時間の負荷要因の考え方などです。
【認定基準改正のポイント】
- 長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確にする
- 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直しする
- 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確にすること
- 対象疾病に「重篤な心不全」を追加
詳しくはこちらをご覧ください→
・厚生労働省【 脳・心臓疾患の労災認定基準を改正】
・脳・心臓疾患の労災認定基準の改正ポイント
今後は、労務管理の「力」がより一層求められます。
労働時間・労働時間以外の労働者の負荷も考慮する労務管理が必要となるでしょう。
当事務所では、心身の健康を守るための様々なサポートも行っています。
気になることがありましたら、お気軽にお問合せください。
管理職研修のテーマは「コミュニケーション力」です。
初任される管理職から、ハイエンドの管理職まで受講いただける管理職研修会。
数社のお客様のご協力をいただき、何度もブラッシュアップしたプログラムになりました。
業界特化型・構成年齢考慮型・少人数制(1名から対応可能)等々、若干のカスタマイズの打ち合わせで、研修が可能です。
尚、顧問契約いただいているお客様には、基本的に無料で提供しています。
研修時間は3時間程度から運営可能です。
Webでの研修も可能です。
ご興味ある方は、是非ご相談ください。